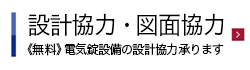高齢者との対話にAI活用を
2024年06月28日 [ 社長コラム ]
雨の季節も猛暑の前奏と思うと有り難いことです。
今月は日経新聞5月9日経済教室
「高齢者との対話にAI活用を」
について書きます。
-------
日本は今後、単独世帯が急増する。
高齢者世帯では
2020年に35%だった単独世帯の割合が
2050年には45%まで増える見通しだ。
未婚者の割合も増えることから、
普段から話す相手が少ない高齢者を前提とした
サービスの見直しが必至である。
自治体は医療・介護事業者などが行う
住民向け業務はその最たるものだ。
いずれも人手不足が顕著な分野であり、
記録作成を含めると訪問や面談は従事時間も長い。
そこで高齢者との接点に対話型AI(人工知能)を
積極的に活用してはどうか。
ただし、相談援助では
面談に専門知見が必要なので、相談の前の
情報提供や現況確認と言った業務に活用するのだ。
例えば高齢者に対話型AIと
毎日様々な話題で話してもらい、その一環で
話の内容に応じて早期にヒトによる面談につなぐ
と言った使い方だ。
高齢者にとって「ちょっと気になることを話せる相手」
として対話型AIサービスを位置づける。
介護予防や退院後のフォローは勿論、地域の金融機関や
交通事業者、薬局や小売業者、インフラ事業者などとも
共用すれば、生活サービスへのアクセスの確保にも
貢献するはずだ。
勿論デジタルデバイド(情報格差)と
AI技術の進化が課題となるが
前者では高知県日高村のように
これから必須の生活インフラとして
高齢者のスマートフォンの活用を広げた
事例も出てきた。
また後者についても、
要介護高齢者のモニタリングを支援する
対話型AI「MICSUS」等の事例もある。
スマホの利用が一般化し技術も進化した今こそ、
新しいやり方に挑戦する時だろう。ただし、
あくまでも技術は手段であって目的では無い。
個人を尊重し、高齢者が自分の思いを言葉にでき、
周りに自分の悩みを相談したり、
投げかけたりしやすくすることを
基本理念とすべきだ。
その上で、理念の具現化のために、公民連携した
サービススキームや会話内容のデータマネジメント、
既存の法制度に基づく業務ルールの見直しなどの
検討を始めるのが良い。地域包括ケアシステムの
目標年である2025年に向けて、
技術を「善くつかう」試行錯誤を始める好機だ。
-------
当社は電気錠を中心に使用していただいている
高齢者施設のお客様が多いです。
周知のとおり3キーやケアロックは
現場でお客様のお困りごとを聞いた営業マンや
技術マンが一から創った製品です。
過去には、安否確認システム、
トイレで一定以上動かないと
事故と見なし報知するシステム、
入居者が危険外出するとお知らせするシステムなど、
30年以上前から実用化してきました。
犬型対話ロボも試作しました。
当社は直接お声を聞くことができる
恵まれた環境にあります。
こちらの問題意識や聞こうとする姿勢があると、
お客様からポロッとヒントが出てきます。
それをすくいあげ、自分の頭、経験に照らして
何かできないか、考えてみましょう。
お客様の笑顔を思い浮かべると
きっと何か発想が生まれてきます。
無いものをあげてもきりがありません。
今手の中にあるものを最大限活用する。
自分の足下、手の中をじっと見つめて考えてみましょう。
今月もありがとうございます。
-------
株式会社JEI
山之口良子